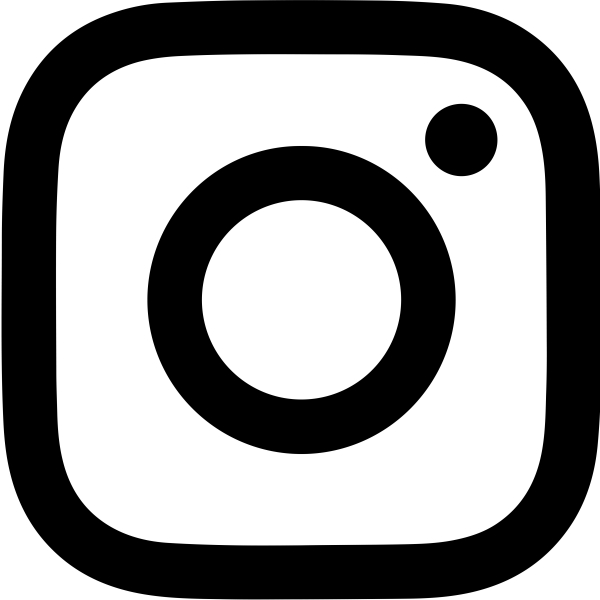カスタム ハンドル関連
-
CB400SF ストリートファイターカスタム ハンドル編
ヤフーオークションで購入して、当店でカスタムするべく、そのまま直ぐ入庫していただきましたCB400SF(NC31)
色々と一気にカスタムしたい衝動もありますが、少しずつカスタムするのも楽しみの一つではないでしょうか!
今回はフトント周りを少々カスタムしていきたいと思います。
まずノーマルのヘッドライトを外します。ヘッドライトの中には各種コネクター・配線がごっそり入っております・・・・
個人売買はどの様な扱いを受けているか分りませんので、フォークオイルの交換です!
カスタムもいいですけど、メンテも大事ですよね!!
フォークオイル交換ついでにフォークブーツを付けました!!
海外製のを用意したのですが、ゴムの質がいかにも『ゴム』な感じて凄くイイです!!
日本に多く出回っているフォークブーツは若干ビニール・・塩ビ・・?っぽい感じでいまいち好きになれずにいました。でも今回のフォークブーツはアタリです!!
ようやくハンドルに入ります!
セパハンを使用しますよ!
デイトナのセパハン用フォーククランプです。
フォーククランプ部とハンドルバー部が別体式のを選びました!
このフォーククランプ、角度が設けられています!
マニュアル通りに付けると、ハンドルバーは下に垂れさがります。
ストリートファイターでは上向きに付けるのがカッコイイです!
しかし、ひっくり返しただけですと、ハンドルバークランプ部のボルトが下から付く為、あまり見せたくない場所が上に向いてしまします・・・・
そこで、左右のクランプを入れ替えますと、ハンドルバークランプ部のボルトは上から付くようになり、見た目もいいかなと思います。
が
今度はフォーククランプ部がノーマルのヘッドライトブラケットに干渉してしまいます・・
A: ハンドルクランプ部のボルトが下から付くのを我慢する
B: ノーマルヘッドライトブラケットを加工する
C: フォーククランプタイプのヘッドライトブラケットを使用する。
一般の方は『A』の我慢する(そもそもそんなの気にしない?)
か、
『C』のフォーククランプタイプのヘッドライトブラケットを使用するのがお手軽かと思いますし、お勧めします。
しかし態々車両を預けていただいておりますので、ここは『B』のノーマルヘッドライトブラケットを加工するでしょう!!!
って事で、干渉する上の部分とノーマルのウインカーが付いていたウインカーステーを切り取りました!!
ヘッドライトブラケット作製は鋼材が届くまで一旦保留とします。
ハンドルに戻ります。
ハンドルバーに取り付けるパーツの長さを測ります。
大体25cm位でしょうかね。
フォーククランプとハンドルバーが別体式のセパハンを選んだ理由がここにあります!
一般的なセパハンは取り付け幅を狭くせまくとする傾向がありますが、ストリートファイターではその逆で広くひろくとした方がカッコよくなる傾向です!!
一体式ですとハンドル長が決まっていますので基本的には好きな長さに出来ません。(溶接って手もありますが)
その点、別体式ですと自由に長さや角度が調整出来ます!!
そうゆう事で、ハンドルバーを作りました!パイプを切っただけ?(笑)
これに角度を付けたりすれば更に調整幅の広いハンドルバーが出来ます。
今回はその必要も無さそうなので、ストレートパイプでいきます!
良い感じです!!
この状態で幅800mmあります!!
しかし、絞り角が無いと手首が痛くなりますので・・
絞りました!つでにグリップもゴツゴツグリップに変更です!!プログリップの804(貫通タイプ)です。そのゴツゴツ感とは裏腹にソフトな握り心地ですよ。
バーの先端が余っているのはバーエンドミラーを付ける為の余白です!
CB400SF ストリートファイターカスタム ヘッドライト編へつづく・・・
Share Buttons with Logos この記事をシェア
ジーザックをフォロー
PR -
motogadget m-Switchの取り付け
モトガジェット製のm-スイッチです。
アルミ削り出しのボディーにステンレス製のボタンスイッチが2つ。
ボディー色:2色、スイッチ色:2色あり、4通りの組合せから選べます!
今日はm-スイッチの取り付け方法をご紹介。
m-スイッチは基本的にハンドル内部に配線を通す用に作られていますので、中通しをしない方はm-スイッチのボディーを削って配線を外に出して下さい。今回はハンドル内部に配線を通しますので省きます。
上記写真、m-スイッチの内部ですが、配線取り付け部の端子がご覧の様に斜めになっていたりします。この状態でハンドルに組みますと、端子部分がハンドルと接触し、ショートの原因となりますので、位置合わせを行って下さい。
ハンドルに対し並行に端子を回しました。
スイッチはねじ込みタイプですので、最終的な端子の位置調整が終わりましたら、中強度のネジロック剤でゆるみ止めを施します。ねじ込む際に工具を使用してはいけません。
m-スイッチはアースタイプのスイッチ回路にも対応しておりまして、中心部分(赤丸部分)にボディーアースポイントが用意されています。ボディーアースする事により、ハンドル内部に通す配線が2本減らせるとゆうメリットがあります!今回はボディーアーススイッチ回路ですので、是非使い所です。勿論、計4本の配線をハンドル内部に通しても構いません。
m-スイッチはアルマイト処理が施されており、アルマイトは導通性がありませんので、ボディーアース方式で接続する時には剥がして使用します。剥がす箇所は緑丸付近がいいでしょう。全部剥がす必要はありません。ハンドルと接触し、かつハンドルの下側にくる位置が理想です。
m-スイッチの中心アースポイント → m-スイッチのボディー部分 → ハンドル → ハンドルポスト → ハンドルポスト固定ボルト。
これらの導通を点検し、導通が無ければ導通する様にアルマイトを剥がしたり、塗装を剥がしたりします。
この車両はハンドルポストがラバーマウントされていますので、ハンドルポスト固定ボルトまで。そこからは配線で車体側にアースします。
これでようやく配線接続に取り掛かれます!!
こちらのツール、オートマチック配線被覆剥き機とでも言いましょうか。レバーを握れば綺麗に被覆が剥けてくれます!剥く長さも6mmから18mmまで調整が可能!対応する太さもバイクで使用するには困りません!「KNIPEX」というドイツのブランドです!10年ほど昔にスナップオンのバンセールスから購入したもので、何処で手に入るかは知りません(笑)でも、相当使える奴です!!
m-スイッチに付属しているアースポイント用の端子です。写真に写っている配線は18ゲージの太さですが、見事に入らず(笑)ですので、20ゲージ位の太さまでワイヤーをカットして入れました。説明書にはこの小さな端子に配線が2本入っている図なのですが、18ゲージの配線では2本は無理です。端子の外側にハンダで2本付けるとゆう策もあるかと思いますが、今回はスイッチから出た2本のアース線を1本にまとめて接続したいと思います。
可動部ではないので、一度ハンドルに固定してしまえば外れる事もないでしょうが、一応ハンダで固定して収縮チューブで保護しておきます。後で手直しも面倒ですので、やれるうちに施しておきます。
そして3本をハンダ付けし、
スイッチ内に収めます。
導通テストを行います。m-スイッチは押している間だけONとなります。
ハンドルに予め開けておいた穴に配線を通します。
2つ目も同じ作業を施し完成!!
スイッチが変わるとカスタム度が大幅にアップしますね!!カッコイイです!!
右側: スタータースイッチ、メーター切り替えスイッチ3本。ブレーキスイッチ2本。ウインカー2本の合計7本。
左側: 右ウインカースイッチ1本。左ウインカースイッチ1本。ハイ/ロー切り替えスイッチ1本。ホーンスイッチ1本。ウインカー2本の合計6本。
これらの配線がハンドル内に収まっておりますので非常にスッキリした外観を得られました!!
m-スイッチを使っては勿論、ノーマルのスイッチボックスでもハンドル内に配線を通す事でスッキリとした外観が得られますし、なにより『カスタムした感』が大きく出ますので、一歩先へ進みたい方は是非チャレンジしてみて下さい。
Share Buttons with Logos この記事をシェア
ジーザックをフォロー
-
CB650C カスタム スタータースイッチ取り付け編
ストリートファイターに人気のワイド&ローなハンドルバー、LSLストリートハンドルバー(スチール製)です!
スタータースイッチを取り付けるべく、作業開始!
背景がゴチャゴチャで申し訳ありません(笑)
今回はこのマスターシリンダーに埋め込みます!
スイッチを埋め込む事によりノーマルの樹脂製スイッチボックスとはおさらば出来、なにより見た目がスッキリしますからね!
クランプ部にスイッチの入る穴を削っていきます。
ちなみにこの工作機械の事を世間では『フライス盤』と呼んでいるそうですが、ジーザックドットコムでは『若干精度のよい穴開け機』と呼んでおります…(笑)フライスとしてはあまり使っていないとゆうもったいなさ…(汗)
はい。スイッチが付きましたよ!
裏はこんな感じ。
今回はトグルスイッチを選択。
またいつかブログに書きますが、左側はモトガジェットのm-スイッチを2連で使用。
右側に1つ使用の合計3つと思っておりましたが、クリアランスの関係でブレーキレバーのストローク量が確保できなく、右側は断念…。
スイッチを取り付けた際、ハンドルの中はこの様な感じになります。
これが、配線を中通しにした際にアルミ製よりスチール製をお薦めする理由です。
スイッチだけでハンドルの半分のラインまで使い、これに配線が付きますのでアルミ製(ハンドル内径14mm)ですとクリアランス的に厳しくなります。このスチール製(ハンドル内径18mm)でしたらスイッチに配線が付き、バーエンドウインカー分の配線を通しても余裕が生まれますね。
配線中通ししない方は全く関係の無い話ですので、アルミ製でもスチール製でもお好みを選択すればOKですし、配線の量によってはアルミ製でも問題ないですしね。ハンドルバーの中に入れる物の量によって選択すればいいかと思います。
後はスイッチに合わせてハンドルに穴を開けるだけです!!←ここが一番大変?
いつもは『若干精度のよい穴開け機』で四角く穴を開けるのですが、何を思ったか「手で出来るかな?」と疑問が生じ、今回は手作業でチャレンジ(笑)ご覧の通り綺麗ではありませんが、手ヤスリだけでも可能ではあります。
ご自身で作業を!と目論んでいる方の参考になりましたかな?
注意は穴の淵に出来るバリ(ささくれ)は綺麗に除去すること!
これを怠ると、バリにより配線の被覆が破けてショートの原因となります。
組み付けて完成!!
いい感じにスイッチが付きましたね!
今回使用したトグルスイッチは(ON)-OFF-(ON)のタイプ、通常はOFF電気が流れず、レバーを倒した時だけON電気が流れるスイッチです。ノーマルのスターターボタンを押しているのがレバーになったタイプですね。IP57規格のスイッチですので、防水防塵で安心して使用できます。
ちなみにIP規格の最初の数字5は「防塵」、6になると「耐塵」。何が違うの??と思いますよね?「耐塵」になると粉塵に対し全く内部に入ってくる事が全く無い構造になるみたいです。ですので、「防塵」は若干内部に入るかもよ…。位ですかね?(笑)
2番目の数字7は「一時的水没」だそうで、水深1mで30分間は耐えられるようです!8だと継続的水没OK、6だと暴噴流OK(消防車位の水圧?)。まぁ、もしハンドルに付けたスイッチが1mも水没したら、スイッチが無事かどうかなんてどうでもいい位の大事件ですよね(笑)バイクに使うのは十分なスペックです。
レバーを右に倒すか左に倒すかで独立した回路となりますので、右はスタータースイッチとして、左はメーターの表示切り替え用にでもしようかな…と考えております。
スイッチタイプも倒すと常時ONになるものもありますし、1つで2役のトグルスイッチは使える奴ですよ!!
左側のスイッチ取り付けは、motogadget m-Switchの取り付けで紹介しておりますので併せてご覧ください。
Share Buttons with Logos この記事をシェア
ジーザックをフォロー